 ミライオンの
ミライオンの
経営力向上ブログ
集客・マーケティング・組織開発・補助金など
経営に関する様々な情報を発信しています

海外進出で差をつける!IRフレームワークを活用したマルチナショナル型戦略のすすめ
IRフレームワークとは? 企業が海外に進出するとき、どの程度本社で「標準化」(国が変わっても製品の規格や機能などを変えない)を進めるか、逆にどの程度現地の市場や文化に合わせて「適応」(その国に合わせて製品の規格や機能などを変える)させるかが大きな経営課題です。I-Rフレームワークは、この「統合(Integration)」と「現地適応(Responsiveness)」のバランスを軸に、国際経営戦略を4つのタイプに整理する考え方です。 なぜ「現地適応」を重視する企業が増えているのか? 海外進出のハードルが下がり、中小企業でも海外市場へ挑戦しやすい環境になりました。このような海外進出において顧客のニーズを掴み、現地事情に合わせた柔軟な対応が求められるケースが増えています。 たとえば、 こちら現地の状況に合わせたローカライズが重要なのは、ご理解いただけるでしょう。 海外顧客への適応を支援する事業も増えている 私は、外国の方の起業や創業の支援をすることもあります。外国人が日本で、「インバウンド観光客に訴求するためのマーケティング支援事業」、「日本の抹茶を海外向けに企画・デザインし販売促進する事業」などの海外顧客向けにローカライズすることを支援する事業を行う外国人の方もいます。 また、現地にいる日本人コーディネーターと連携して、海外の市場調査や販売会社との提携を進めるケースもあります。しかし、これらのローカライズを支援する事業者はピンキリで、酷い現地レポートが送られてくることもあります。海外進出においてこれらの方の協力はとてもありがたいのですが、選定は比較検討しながら慎重に行いたいものです。 「マルチナショナル型」の特徴とメリット I-Rフレームワークの中で「標準化よりも現地適応をより重視」するマルチナショナル型をピックアップして、本記事ではその特徴と利点を整理します。 3-1.特徴 3-2.メリット マルチナショナル型導入に向けたポイント 現地適応を最重要視する方針を取り入れるには、本社と海外拠点の役割分担やコミュニケーション体制を整備することが大切ではありません。 中小企業が「マルチナショナル型」を活かすために 中小企業の場合、大企業に比べて経営資源が限られています。 そのため、現地拠点への集中投資や大幅な分権化はリスクとも背中合わせです。 まとめ I-Rフレームワークを
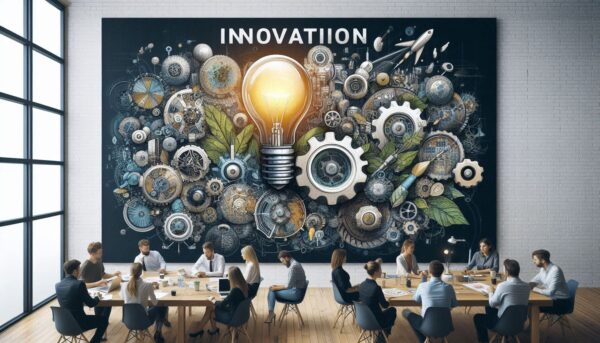
自社製品の市場段階を見据え、限られた資源を最大化する|中小企業経営者のためのA-Uモデル解説
産業発展の段階と革新のモデル(A-Uモデル)とは?企業が成長・発展する過程では、製品やサービスをめぐる革新(技術革新)の形態が変化していくと言われています。これを体系的に示したものが、W.アバナシーとJ.アッターバックによる「A-Uモデル」です。中小企業の経営においても、製造業にかかわらず、イノベーションというものを考えるのにおいて、とても有用な考え方ですので、中小企業経営における活用という視点で、A-Uモデルを解説します。 AUモデルの概要 AUモデルでは、産業がまだ新しい段階では製品革新(ラディカル・イノベーション)が前向きに立ち上がり、次世代市場で「標準的な設計」が定まると、主流の革新が工程革新(プロセス革新)や小さな改良をインクリ(漸進的)イノベーションに移行すると説明されています。 1-1. 産業初期:ラディカル・イノベーション 1-2. ドミナントデザインの出現 1-3. 産業の成熟:工程革新・インクリメンタルイノベーション A-Uモデルが示す変化と中小企業への示唆 2-1. 変化するイノベーションの注目点 2-2. ドミナントデザインと組織設計 2-3. 各種イノベーションの代表的な具体例 ここでは、AU-モデルで示される主な革新の種類ごとに、代表的な具体例を一つずつ挙げさせていただきます。 中小企業がA-Uモデルを活用するポイント まとめ A-Uモデルは、産業発展とイノベーションの関係を理解するための強力なフレームワークです。 市場の動向と自社の強みを見極めながら、市場のイノベーション形態を意識することで、戦略の優先度やリスク管理に対するヒントを得られるでしょう。 ぜひA-Uモデルを活用して、自社のステージに合った取り組みを検討してみてください。 <お役立ちポイント> 自社がどのフェーズにあるかを客観的に把握し、A-Uモデルを参考に最適なアイデアを戦略を描いてみてください。

衰退市場でも勝ち残る!衰退市場の具体例と衰退市場で取れる4つの基本戦略を徹底解説
「売上が伸びていたはずの市場が、長期的に見て縮小し始めている…」こうした状況に直面したとき、企業はどのような手を打つべきなのでしょうか。大手企業ばかりでなく、中小企業でも十分に使える戦略があります。ポイントは、限られた需要の中で自社の強みを最大限に活かしながら、どのように利益を確保・拡大していくかです。本記事では、衰退市場において有効とされる4つの基本戦略をわかりやすく解説します。 1. 衰退市場とは? 衰退市場とは、景気の波や一時的な流行の変動ではなく、長期にわたって需要や販売数量そのものが減少し続けている市場(今後も市場の縮小が見込まれている市場)を指します。技術革新・人口動態の変化・消費者ニーズの変化など多岐にわたる要因が背景となり、縮小傾向が続くのが特徴です。 衰退市場では、売上が減っている中で固定費(売上高に関係なく発生する一定のコスト)をどう回収するかが重要になります。衰退市場では、ライバルとなる競争相手が市場から撤退することが期待できますが、競争相手が少なくなっても、買い手が価格に敏感だったり、強力な競合が価格を引き下げたりすると、激しい価格競争に巻き込まれるリスクがあります。 2.衰退市場の具体例 衰退市場として代表的に挙げられるのが、次のような分野です。これらはいずれも、技術革新や消費者のライフスタイル変化などによって長期的に需要が落ち込んでいる市場です。 (1) CD・DVDなどの物理メディア市場 音楽・映像のストリーミングサービスが普及したことで、CDやDVD、Blu-rayなど物理メディアの売上は縮小傾向にあります。特典やコレクター向け商品で一定の需要は存在するものの、全体としては配信サービスへの移行が加速しています。 衰退要因の例 (2) フィルムカメラ・写真現像市場 デジタルカメラやスマートフォンのカメラ機能が向上し、フィルム写真の現像需要は大幅に減少しました。かつては街中に多く見られた写真現像店も激減しています。ただし、アナログの味わいを好むファン向けや、インスタントカメラ・チェキなどの特定のニッチ需要は根強く存在します。 衰退要因の例 (3) 紙媒体の新聞・雑誌市場 インターネットや電子書籍の普及によって、紙媒体全体の発行部数・売上は年々減少を続けています。速報性の高いニュースはオンラインにシフトし、若年層を中心に紙離れが進んでいま
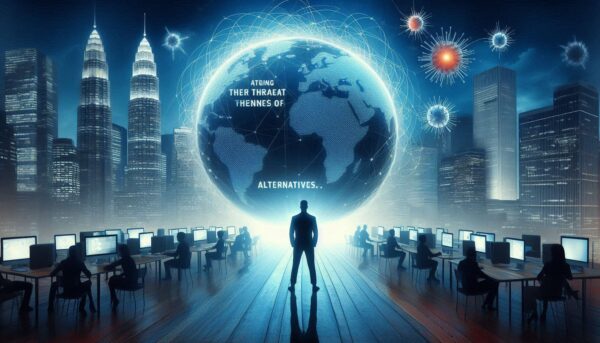
事業立ち上げで見落としがちな「代替品の脅威」とは?
事業立ち上げで見落としがちな「代替品の脅威」とは? 新規事業を創業したり、新規事業を立ち上げたりする際、ビジネスプランを考えるために「市場調査」や「競合分析」を行うことは非常に大切です。これから参入しようとしている市場において、既に事業を行っているどんなライバルがいるかを知ることで、じゃあ自分たちは、「何を強みに」「何で差別化をして」「価格はいくらにするのか」といったことを決めることに役立てられます。創業や新規事業の立ち上げにおいて、このすでにいるライバルたちを調べるということは、絶対に外せない行動だと考えます。 ここでライバルとなるのは、既に商品を販売、あるいはサービスを提供している企業だけでなく、商品・サービスは全く異なる形だけど、同様の顧客ニーズを満たす「代替品」を提供している事業者も含めまれます。 本記事では、M.ポーターの「5フォース分析」に登場する「代替品の検討」に焦点を当て、特に創業者や中小企業が新規事業を選ぶ際のヒントとなるよう解説していきます。 1. 「代替品の脅威」とは? 新たな事業を検討する際に必ず押さえておきたいポイントのひとつが、「自社が参入しようとしている業界には、どんな代替品が存在するのか」という視点です。米国の経営学者マイケル・ポーターのファイブフォース分析(5フォース分析)では、業界の外からの脅威(競争要因)として、「新規参入企業の検討」と並んで「代替品の検討」が挙げられています。これは、顧客の同じようなニーズを満たす別の製品・サービスが台頭することで、その製品・サービスのニーズが奪われ、収益性が低下する可能性があることを示しています。 ファイブフォース分析は、米国の経営学者マイケル・ポーターが提唱した業界構造の分析手法です。以下の5つの外部の利害関係者との綱引き関係(フォース)を捉えることで、業界全体の競争構造と収益性を読み解く方法です。 このうち「代替品の脅威」は、業界の外部に視点を置く視野として捉えられ、既存の製品・サービスと同等以上の価値を提供する何かが出現した場合のリスクを示します。 2. 代替品が存在する可能性がもたらすリスク (1)価格競争の激化 代替品が存在すると、すでに存在する同種の製品やサービスと同様に、顧客は「より安く」「より手軽に」ニーズを満たす選択肢と認識されます。結果、製品・サービスの価格にも影響が生ま

O.ウィリアムソンの取引コスト理論で実現するコスト最適化と垂直統合戦略
はじめに 経営者の皆さまは日々、「外注すべきか、それとも自社でまかなうべきか」という悩みに直面していませんか?たとえば、製品の一部を外注してコストを抑えたいけれど、品質や納期のコントロールも気になる。あるいは、外注先との交渉や契約上のリスクが増大している。こうした取引にまつわるコストは、実は企業経営を大きく左右するポイントです。 そこで注目したいのがO.ウィリアムソン(Oliver E. Williamson)が提唱した「取引コスト理論(Transaction Cost Theory)」。本記事では、この理論を経営に落とし込むヒントをわかりやすく解説し、「どのようにコストを最適化し、ビジネスを安定・成長させるか」のヒントをお伝えします。近年、企業戦略の一環として「垂直統合(vertical integration)」が注目されています。製品の開発や製造、流通、販売など、商流(バリューチェーン)の複数段階を一貫して自社で手掛けることで、コストの削減や品質の維持、安定したサプライチェーンの実現もたらす可能性があるためです。 しかし、事業戦略において垂直統合が常に正解となるとは当然限りません。その判断において参考となるのがO.ウィリアムソン(Oliver E. Williamson)による取引コスト理論(transaction cost theory)なのです。 取引コスト理論とは何か? 取引コスト理論とは、企業が市場における外部の企業と取引をする際に生じるさまざまなコストを最小化する視点から、最適な組織構造や内製か外注化などの意思決定を捉える考え方です。 情報収集コスト:取引相手や価格情報を調べるための手間 交渉コスト:契約内容や条件調整にかかる時間や費用 監督・管理コスト:契約後に納期や品質を管理するためのコスト これら「外部とのやり取りで発生するコスト(取引コスト)」が「自社で行うための設備投資や人件費、さらにそれらを管理するコスト(内部管理コスト)」より大きい場合、企業は外注ではなく自社で業務を行う(垂直統合する)ほうが総合的に効率的と判断できます。このような取引コストと内部管理コストに着目して意思決定に役立てるのです。 「関係特殊的資産」が意思決定を左右する 取引コスト理論では、特に「関係特殊的資産(Relationship-specific Asset)」の

【見えざる資産とは?】伊丹敬之が提唱する無形資産の重要性と競争優位への活かし方
近年、企業経営の現場で注目されている「見えざる資産」という概念。これは、企業の持つ有形資産(建物・機械設備など)とは異なり、目に見えない無形の資産を指します。近年、企業の競争力は人材や技術力、ノウハウ、ブランド、認知度など、つまり有形資産だけでは測れない部分の影響が大きくなっており、「見えざる資産」の重要性はますます高まっています。本記事では、伊丹敬之氏が提唱する「見えざる資産」をテーマに、その定義や具体例、企業経営における活用方法などを解説します。 1. 見えざる資産とは何か? 経営学者で一橋大学名誉教授の伊丹敬之(いたみ・のりゆき)氏は、経営資源を「ヒト・モノ・カネ・情報」の四つに分類し、このうち情報的経営資源(目に見えない資源)を「見えざる資産」と呼びました。具体的には、以下のようなものが挙げられます。 有形の資産(設備や建物など)が視覚的に把握しやすいのに対し、「見えざる資産」は目に見えないため、一見すると評価や管理が難しく感じられるかもしれません。しかし、企業の競争優位を生み出す重要な源泉となるため、経営上の注目度が高い要素でもあります。 見えざる資産と、似たような意味を持つ言葉としては、「知的資産」や「知的財産」があります。「知的資産」は、「知的財産」とほぼ同義であるといってよく、目に見えない無形資産を広範に含む概念です。一方で、「知的財産」の方は、広義には「見えざる資産」や「知的資産」とほぼ同じ意味合いで使用されることがありますが、「知的財産」は狭義には「特許権」や「商標権」などの知的財産権という法的に保護された権利を意味します。 2. 見えざる資産がもたらす競争優位の例 「見えざる資産」は無形で模倣が困難な場合が多く、競合他社との差別化を生み出す原動力となります。例えば、以下のような強みを生み出せるのです。 3. 見えざる資産の特徴:多重利用が可能 「見えざる資産」は、有形資産と比較して同時多重利用がしやすいという強みがあります。例えば、ブランドのイメージを確立すると、別の製品ジャンルやサービス領域にもブランド力を転用できます。また、技術やノウハウなどの知見は、同じ組織内の複数部門で共有することで、企業全体のレベルアップにつながります。 4. 中小企業にこそ見えざる資産の活用が重要 大企業だけでなく、中小企業にとっても「見えざる資産」は大きな武器に
