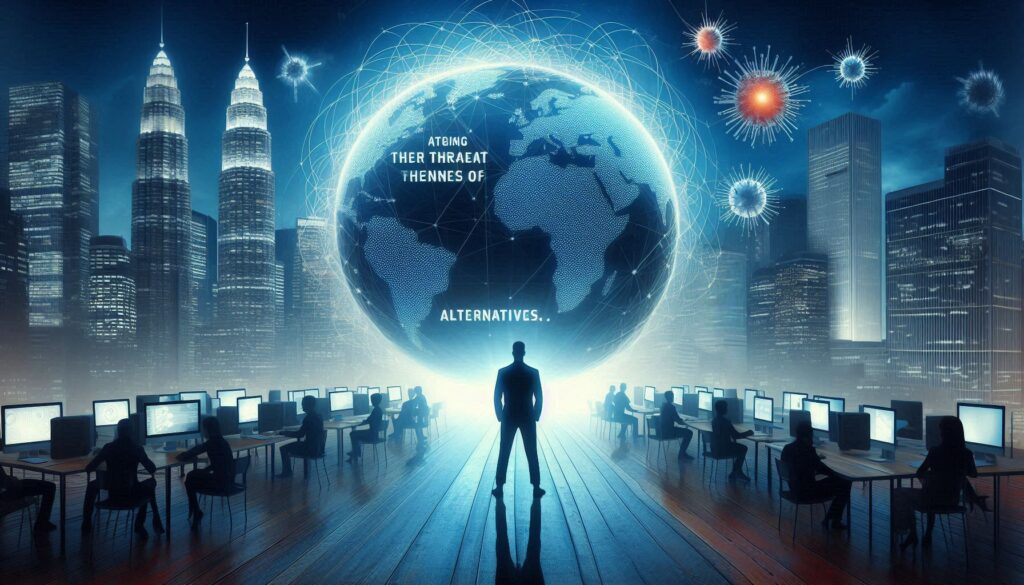エフェクチュエーションとは?不確実な時代の起業戦略と5つの原則
エフェクチュエーションとは何か? エフェクチュエーション(Effectuation)とは、起業家が不確実な状況下で柔軟かつ主体的に事業を進める際に用いる意思決定のスタイルです。一般的には、あらかじめ定めた「目的」から逆算して手段を検討する手法(コーゼーション:Causation)と対比されます。エフェクチュエーションは、「いま自分が持っている手段を活かして、何ができるかを探りながら事業をデザインしていく」とう発想が特徴です。 不確実性が高まる現代では、どれだけ事前に計画や予測を立てても、思いがけない出来事や環境変化によって計画が崩れてしまいやすくなっています。こうした状況下では、事前の予測を正確に立てるよりも、「まず手を動かし、自分にできることを実行してみて、そこから得た知見や周囲との関係性を活かしながら柔軟に修正していく」アプローチが有効となるケースが多いのです。 このエフェクチュエーションは、経営学者のサラス・サラスバシーが多くの起業家に対して、スタートアップの過程で直面する典型的な10の意思決定課題について回答を求め、その思考プロセスを分析し、共通項を抽出して後天的に学習可能な理論として体系化したものです。これから起業・創業を考えている方には、実践のヒントやアイデアが数多く詰まっている理論だといえるでしょう。私もとても好きで、影響を受けている考え方です。 この記事では、これから事業を立ち上げようとしている創業者の方に向けて、エフェクチュエーションの基本的な考え方と、実際に活用するときのポイントを解説します。 エフェクチュエーションの5つの原則 エフェクチュエーションには、以下の5つの行動原則があるとされています。いずれも「不確実な未来を予測する」よりも、「いまある手段や人脈、そして突発的に起きた出来事を活かす」姿勢が重要視されます。各原則を下記に解説します。 1. 手中の鳥(Bird in Hand)の原則 手中の鳥(Bird in Hand)の原則とは、「今、手元にある資源やスキル、ネットワークを起点に事業機会を探っていく」という考え方です。 2. 許容可能な損失(Affordable Loss)の原則 許容可能な損失(Affordable Loss)の原則とは、「どれだけ利益を得られるか」よりも「どれだけ損失を許容できるか」を基準に意思決定を行う考え方で
エフェクチュエーションとは?不確実な時代の起業戦略と5つの原則 続きを読む »