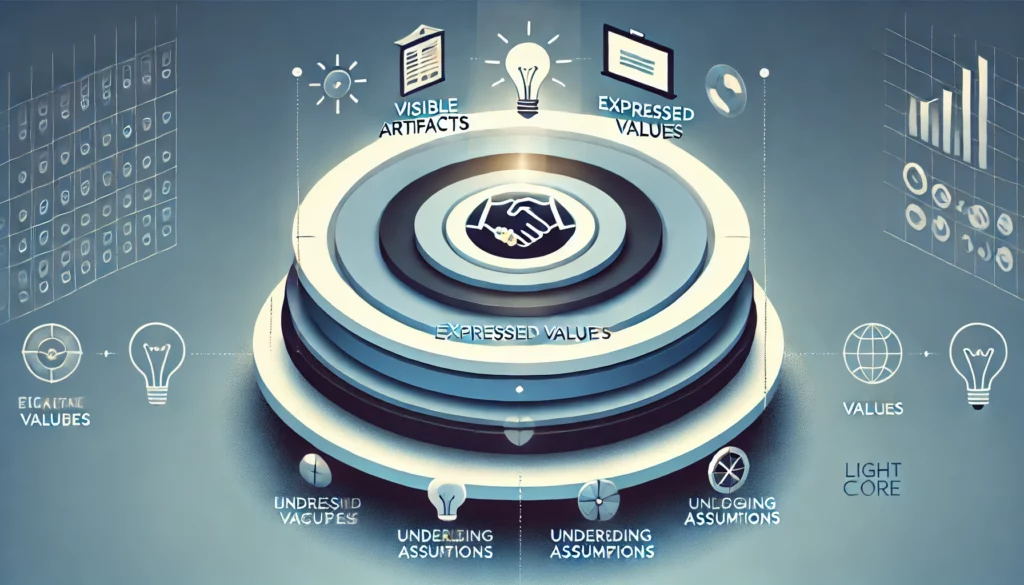O.ウィリアムソンの取引コスト理論で実現するコスト最適化と垂直統合戦略
はじめに 経営者の皆さまは日々、「外注すべきか、それとも自社でまかなうべきか」という悩みに直面していませんか?たとえば、製品の一部を外注してコストを抑えたいけれど、品質や納期のコントロールも気になる。あるいは、外注先との交渉や契約上のリスクが増大している。こうした取引にまつわるコストは、実は企業経営を大きく左右するポイントです。 そこで注目したいのがO.ウィリアムソン(Oliver E. Williamson)が提唱した「取引コスト理論(Transaction Cost Theory)」。本記事では、この理論を経営に落とし込むヒントをわかりやすく解説し、「どのようにコストを最適化し、ビジネスを安定・成長させるか」のヒントをお伝えします。近年、企業戦略の一環として「垂直統合(vertical integration)」が注目されています。製品の開発や製造、流通、販売など、商流(バリューチェーン)の複数段階を一貫して自社で手掛けることで、コストの削減や品質の維持、安定したサプライチェーンの実現もたらす可能性があるためです。 しかし、事業戦略において垂直統合が常に正解となるとは当然限りません。その判断において参考となるのがO.ウィリアムソン(Oliver E. Williamson)による取引コスト理論(transaction cost theory)なのです。 取引コスト理論とは何か? 取引コスト理論とは、企業が市場における外部の企業と取引をする際に生じるさまざまなコストを最小化する視点から、最適な組織構造や内製か外注化などの意思決定を捉える考え方です。 情報収集コスト:取引相手や価格情報を調べるための手間 交渉コスト:契約内容や条件調整にかかる時間や費用 監督・管理コスト:契約後に納期や品質を管理するためのコスト これら「外部とのやり取りで発生するコスト(取引コスト)」が「自社で行うための設備投資や人件費、さらにそれらを管理するコスト(内部管理コスト)」より大きい場合、企業は外注ではなく自社で業務を行う(垂直統合する)ほうが総合的に効率的と判断できます。このような取引コストと内部管理コストに着目して意思決定に役立てるのです。 「関係特殊的資産」が意思決定を左右する 取引コスト理論では、特に「関係特殊的資産(Relationship-specific Asset)」の
O.ウィリアムソンの取引コスト理論で実現するコスト最適化と垂直統合戦略 続きを読む »